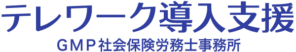就業規則の改定などで対応できることが多くあります。
労働時間の柔軟な運用へ改定
在宅勤務というと、多くの人が毎日在宅で仕事をすると誤解しがちですが、日本の企業の場合は、多くが週に1日か2日の在宅勤務です。
モバイル勤務の場合も直行・直帰を認めるのか、その場合部分在宅勤務も可能とするのか。サテライトオフィス勤務も他社と共有型のサテライトオフィスにするのか、自社専用にするのか、など決めるべき項目は多岐にわたります。
休憩時間に関する労使協定
テレワークを行う労働者について、労使協定により、休憩時間の一斉付与の原則を適用除外とすることができます。
在宅勤務等のテレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じやすいと考えられます(いわゆる中抜け時間)。
中抜け時間について、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合その開始と終了の時間を報告させる等により、休憩時間として扱い、労働者のニーズに応じ、始業時刻を繰り上げる、又は終業時刻を繰り下げるこや、休憩時間ではなく時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが可能です。
テレワークの費用負担
自宅でテレワークを実施する場合に必要な通信費や光熱費、ICT機器などの費用負担については、あらかじめ十分に話し合い、就業規則に定めておくことが望まれます。多くの企業ではインターネット環境などはすでにほとんどの家庭で導入しており、追加負担も発生しないため、補助はしていません。
音声通話については、携帯電話を会社支給したり、個人のスマートフォンの請求を私的利用と会社利用に分けて請求するシステムを導入したりする場合があります。
ICT機器については、会社支給のものを利用したり、BYOD(Bring Your Own Device)で個人のPCをリモートアクセスで利用したりする場合もあります。
光熱費については、企業によって若干の補助をする場合もありますが、多くの企業では自己負担としています。ただし、在宅勤務の日数が多い場合には会社からの補助を検討することが望まれます。
通勤費については、テレワークの頻度によって検討すべきです。週に3日以上在宅勤務する場合は、定期代の支給ではなく、都度精算した方が割安となる場合があるからです。
サテライトオフィス利用料金は会社負担とすべきです。
在宅勤務手当
通勤手当を在宅勤務手当に切り替える企業も少なくありません。
仕事中にエアコンをかける、Wi-Fiを契約するなどと、在宅で働くと光熱費や通信費が増えがちです。在宅勤務手当を支給すると、支出の穴埋めが可能です。なお、デスクや椅子を購入する、ワークスペースを確保する、文房具を購入するなど、在宅勤務手当の使いみちは従業員により異なります。
セキュリティ規程
テレワークはセキュリティの管理が難しいという人が多いです。しかし、リモートデスクトップ方式や仮想デスクトップ方式(Virtual Desktop Infrastructure)、クラウドサービスなどを利用すれば、社外であってもセキュリティを確保した上で業務遂行することは可能です。
総務省 テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン